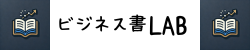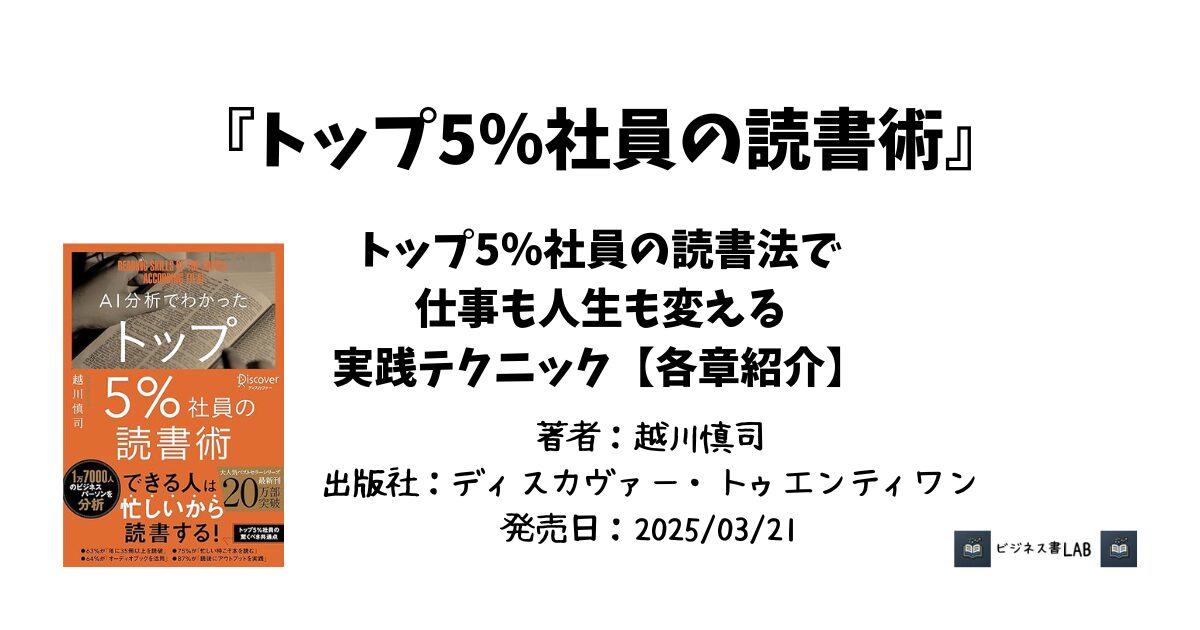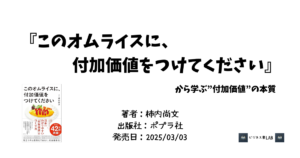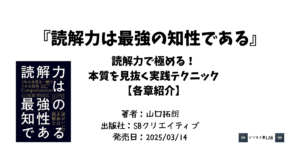この記事では「AI分析でわかったトップ5%社員の読書術」を紹介します。
現代のビジネスシーンで活躍するトップ5%社員の秘密は、その圧倒的な読書習慣にありました。
本書「AI分析でわかったトップ5%社員の読書術」は、忙しい日々の中でも自己成長と効率を追求するための具体的なテクニックを、科学的な根拠と実践例に基づいて解説しています。
「読書=時間の浪費」と思い込んでいる人に、環境設定からアウトプットまですぐに使えるノウハウが満載の1冊です。
オススメの人
キャリアップを目指すサラリーマン
多くの成功した社員たちに共通する習慣として、読書があります。
心理学的研究によれば、読書は単なる知識の獲得以上の効果があり、
論理的思考や意思決定能力を磨く重要な手段となっています。
忙しくても自己成長を諦めたくない人
本当に忙しい人ほど、隙間時間を活用して読書を習慣づけています。
環境心理学や認知科学の研究によれば、読書環境を整えることで集中力を高め、
限られた時間を最大限に活用できることがわかっています。
読書習慣を確立できない人
本が積まれたままになっている、読み書けの本が増える…こんな人が多いはずです。
本書では、読書習慣を身につけるためのヒントが丁寧に解説されています。
各章の紹介
各章の紹介を簡単にしていきます。この書籍の目次は以下となります。
序章 トップ5%社員たちの実態
第1章 読書を習慣にできない理由
第2章 5%社員のユニークな本選び
第3章 読書は「準備」で決まる
第4章 今日からできる! 再現可能な5%社員の読書
第5章 5%社員は「読後」に差をつける
序章

普段、読書をする?



読みたいとは思ってるけど…忙しくてできていないよ。



3人に1人は、読書をほとんどしていないんだ。
しかも、20代~60代のどの年代でも同じなんだ。
「読書はほとんどしない」は35%
株式会社 クロス・マーケティング/読書に関する調査(2020年)



やっぱり、みんな読書していないんだね!



みんな読んでないからって安心しちゃダメだよ。
本書の中では、こんなデータがあるよ!
年に平均で43.2冊の読書をし、うち63%は35冊以上読んでいました。
トップ5%社員の読書術(P.16)



平均で43.2冊?!
そうすると…毎月最低でも3冊以上読んでいるのか。
・トップ5%社員の読書量や行動パターン
トップ5%の社員たちは、膨大な読書量と多様なインプット手法により、
短期間で他社の経験を吸収し自己成長を吸収しています。
忙しい限られた日々の中で読書をすることを習慣づけることは難しいはずです。
だからこそ、紙の本だけでなくオーディオブックを利用することによって、
隙間時間を有効に使って読書をしていることが分かります。
第1章 読書を習慣にできない理由



なぜ読書が習慣にできないと思う?



やっぱり忙しいから?



日本人は働きすぎているって聞くけど、
労働時間は昔に比べると減っているってデータもあるんだ。
日本の平均年間総実労働時間を中期的にみると(中略)
労働政策研究・研修機構/データブック国際労働比較2024年より引用
1988年時点は2092時間から、2022年には1607時間となっている。



スマホの利用時間は、2019年から2023年で約1.4倍に増加しているんだ。



やっぱり疲れて帰ったら、まずSNSチェックして…
寝る前にはゲームや動画見たりするかな。



体を休めることやリラックスする時間も、大事!
ただ隙間時間なら読書にあてる時間はあるんじゃないかな!
・活字アレルギー
・読書習慣の妨げとなる心理的・環境的障壁
第2章 5%社員のユニークな本選び



セレンディピティの法則ってそもそもどんな法則なの?



セレンディピティの法則は、本の選び方に用いている方法論なんだ。



セレンディピティの法則って、ただ偶然に頼るだけじゃないの?
どうやって戦略的に活かすの?



トップ5%社員は普段の読書ルーチンに『意図的な偶然』を組み込んでいるんだ。例えば、『普段は選ばないジャンルの本も敢えて手に取る』ことで、新しい視点やアイデアが生まれるんだよ。



なるほど。つまり、偶然を狙うのではなく、
あえて未知にチャレンジする戦略ってことか。



その通り!それがポートフォリオバランスにもつながるんだ。
読書のポートフォリオを構築することで、特定の分野に偏らず、
広い知識や柔軟な思考を手に入れることができるんだ。
・セレンディピティの法則
・ポートフォリオバランス
第2章では、成果を上げている社員たちが実践している本の選び方について。
「セレンディピティ5対2の法則」と呼ばれる方法では、普段読む分野の本5冊に対して、全く新しい分野の本を2冊意識的に選ぶことで、思いがけない発見や気づきを得やすくなるそうです。
また、専門書と教養書をバランスよく読むことで、仕事に直結する知識と広い視野の両方を身につけ、日々の問題解決や新しいアイデアの創出につなげている様子も描かれています。
第3章 読書は「準備」で決まる



読書するとき、準備ってそんなに重要かな?



例えば、スマホを遠ざけるだけで集中力がぐっと高まるよ。「自分はできる」と自らを肯定するアファメーションも読む内容の吸収に効果があるんだ。



読書を始めても、途中でやめたくなることがあるんだよね…最初は「読もう!」って思ってるのに…



あるある!でも、それを防ぐ心理テクニックがあるんだ。
「サンクコスト効果」って聞いたことないかな?



なんとなく聞いたことあるけど、具体的にどういうものなの?



簡単に言うと、一度何かに時間やお金を使うと、それを無駄にしたくないって思う心理のこと。例えば、映画のチケットを買ったら、途中でつまらなくても最後まで観ちゃうことってあるよね?



あー、あるある。でも読書にも応用できるの?



本を買って「この本は絶対に読む」って決めたり、途中まで読んだ内容をメモに残しておくと、サンクコスト効果が働いて、途中でやめにくくなるんだよ。
・環境づくり
・アファメーション
・サンクコスト効果
第3章「読書は準備で決まる」では、単に本を手に取るだけでなく、物理的・精神的な環境づくりの重要性が書かれています。読書に集中できる環境を確保し、スマホなどの誘惑を遠ざけることで、私たちの集中力は高まり、内容が頭に入りやすくなるのです。
心の準備も同様に大切です。アファメーションを活用して自己肯定感を育むことは、読書を続ける強力な心理的支えになります。その結果、知識の吸収率も自然と向上していきます。
こうした物理的・心理的な準備が組み合わさったとき、読書は単なる情報収集から、自己成長を促す価値のある時間へと変わっていくのです。
第4章 今日からできる!再現可能な5%社員の読書法



本買うんだけど、読む時間がなくて積読が増えていく…



購入したらまず10ページだけ読むといいよ!そうすると、内容への没入感が高まるよ。あとがきを先に読むというのも、全体像を掴む助けになるからおすすめだよ。



オーディブルは使ったことある?本書の中で紹介されているけど、5%社員の多くがオーディブルを使っているんだ。



CMで見たことあるけど…まだ使ったことないかな。



オーディブルなら通勤中や家事をしながら効率的に読書ができるよ。小説は情景を思い浮かべたり感情が入ってくるから本の種類によっては、ながら聞きは相性が良くないこともある。だから、オーディブルを始めるときは、ビジネス書をまずは聞いてみるのがおすすめ!
・購入したら即読む
・あとがきを先に
・オーディブル
第4章では、読書をより実践的かつ効果的にするための具体例が詳細されています。
「購入したら即読む」という方法は、購入直後の高揚感を利用して最初の一歩を踏み出す大切さを説いています。また「あとがきを先に読む」というアプローチは、その本が伝えたい革新を先に把握し、読み進める際の期待感を高める効果も期待できます。
オーディブルはCMもやっているので知っている人は多いのではないでしょうか。
忙しい現代人にとって、耳で聴く読書法が新たな知識吸収の手段として紹介されています。本書の中では、著者はこのように書いています。
5%社員の多くは1.5倍速で聴いているというのです。
トップ5%社員の読書術(P.153)
本書の中では他にもマルチリーディングなどのテクニックが紹介されています。これらのテクニックを組み合わせることで、誰でも再現可能な読書法が実現します。
第5章 5%社員は「読後」に差をつける



読書が終わった後、どうしてすぐにアウトプットするのが大切なの?



読後10分以内にアウトプットすることで、記憶が鮮明に残り、理解がより深まるから。学びを定着させるカギとしては有効だよ。



3Iフレームワークって?



Information(情報)
Insight(洞察)
Intelligence(知恵)
これら3つのIで「3Iフレームワーク」と本書では紹介されているよ。



具体的にはどういうことなの?



書籍から情報を得て、その情報を基に自分事に落とし込む、そして落とし込んだ結果を検証していくという考え方だよ。
詳しくは本書の中で3Iフレームワークを、実際に3冊の書籍を「3I」で整理しているからぜひチェックしてみて!
・読後10分以内のアウトプット
・3Iフレームワーク
第5章は、読書の効果を最大限に引き出すための秘訣として、読了直後のアウトプットの大切さを説いています。さらに注目すべきこととして「3Iフレームワーク」の活用です。3つのプロセスを踏むことで、単なる情報集めを超えた本当の知識習得が可能になるわけです。
このアプローチを続けることで、読書から得た学びは一時的なものではなく、長期的な成長へとつながっていくでしょう。読書の真価は、本を閉じた後にこそ発揮されるのかもしれませんね。
さいごに
この記事では「AI分析でわかったトップ5%社員の読書術」を紹介しました。
本書を通して、トップ社員がどのように読書を通じて自己を高め、仕事や人生に活かしているのか、その疑問に迫ることができました。
「忙しいから…」と読書をしない理由を考えるくらいなら、その瞬間に本を開いてみてください。本書では、具体的な読書術が紹介されていて、どれも誰でも明日から実践できる内容ばかりです!
個人によって合う合わないはあるかもしれませんが、その結果こそが重要です。
ぜひ本書を手に取って、明日から新しい読書習慣をはじめてみませんか。