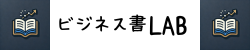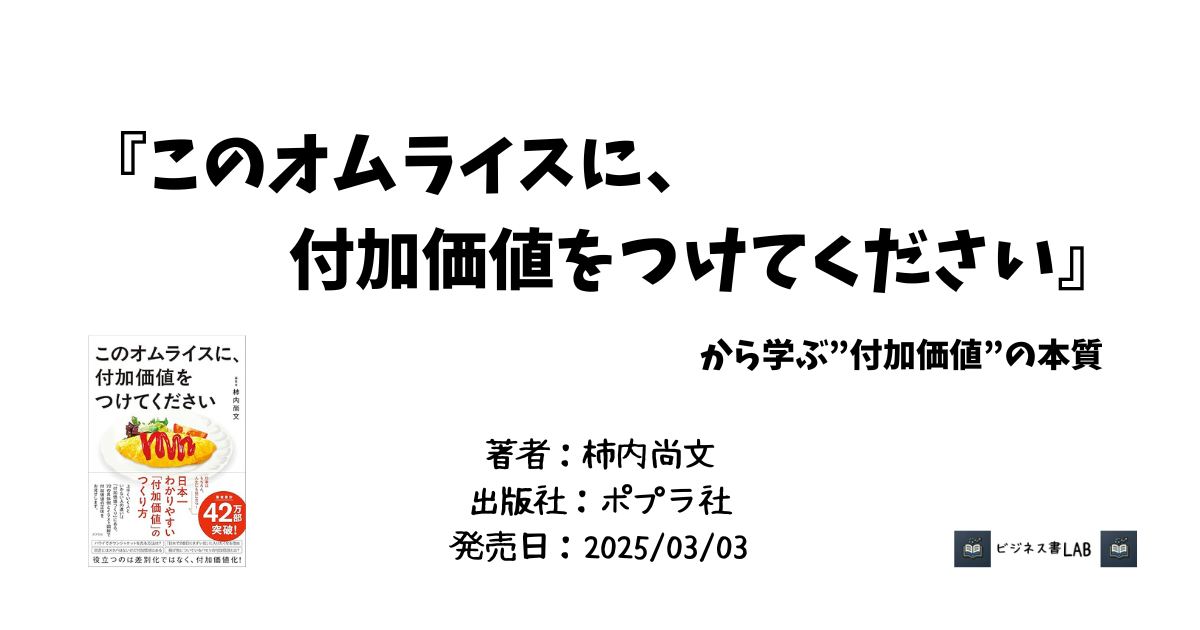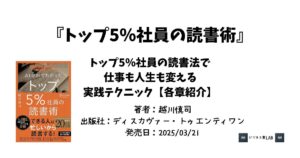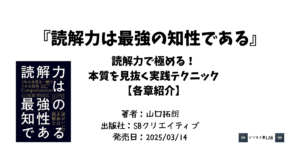この記事では、柿内尚文さんのビジネス書「このオムライスに、付加価値をつけてください」を紹介します。
本書は「オムライス」を題材に、どのように付加価値を創出し、ビジネスや日常生活に活かすかを解説した一冊です。累計40万部を超えるベストセラー作家が提案する「付加価値化」メソッドは、明日から使えるフレームワークとして広い分野で応用可能な内容になっています。
「このオムライスに、付加価値をつけてください」の概要
本書「このオムライスに、付加価値をつけてください」は、柿内尚文さんの著書です。
| タイトル | このオムライスに、付加価値をつけてください |
| 著者 | 柿内 尚文 |
| 出版社 | ポプラ社 |
| 発売日 | 2025年3月3日 |
こんな人におすすめ
・差別化戦略がうまくいかない人
・キャリアアップを目指すサラリーマン
・BtoB企業で営業をしている人
「このオムライスに、付加価値をつけてください」各章まとめ
各章には、どんなことが書かれているのか少し紹介していきます。
第1章 付加価値とは何か

付加価値ってなにか説明できる?



オムライスにトッピングしたらそれは付加価値じゃないの?



著者の柿内さんは、こんなことを著書の中で言っているよ。
「付加されたもの=付加価値」とは限りません。
このオムライスに、付加価値をつけてください(P.52)



トッピングはただ追加しただけで、
付加価値にはならないんだ。



オムライスに金粉とかトッピングしたら
豪華だし華やかな感じになるよ!?



たしかに見た目は豪華になるよね。
でも、それは不要価値になっている可能性が高い。
既存価値:想定内の価値
付加価値:想定外の価値
不要価値:付加価値になっていないこと
このオムライスに、付加価値をつけてください(P.55)
付加価値って、本書を読むと身近なものだということが分かります。
付加価値というワードは、ビジネス用語のように感じませんか?
付加価値と聞くと「ちょっとした特別感」や「見た目の豪華さ」と認識してる人は多いんじゃないでしょうか。
付加価値というのは、多くの人の生活を豊かにする可能性を秘めているワードなのです。
付加価値をつくることができると、人生をより豊かにおもしろく変えることができる~
このオムライスに、付加価値をつけてください(P.68)
第2章 付加価値をどうつくるのか?
この章では具体的な付加価値のつくり方として、
「プロローグ化」や「インパクト化」が紹介されています。



著者は第2章でブームについて以下のように説明しています。
ブームは「付加価値→既存価値→不要価値」
このオムライスに、付加価値をつけてください(P.119)



最近、SNSで流行ってるあの新しいガジェット、どう思う?



最初は「これがあると生活が便利になる!」って付加価値を感じたけど、今はもうどこにでもある感じだね。



まさに「付加価値→既存価値→不要価値」のサイクルだよね。最初は新鮮で価値が高かったのに、次第に「普通」になってしまう。



じゃあいつかは特に必要のないもの、いわゆる不要価値になってしまうんだね?!流行りだからといってずっと価値があるわけじゃないのか!



そうなんだ。ブームの裏側には常にこのサイクルが潜んでいるってこと。企業やクリエイターは常に次の「付加価値」を見つけ続けなきゃいけないんだね。
第3章 自分の付加価値をつくる
この章は、多くのサラリーマンにとって必見の内容です!



付加価値って物だけじゃないの??



それは誤解だよ!
付加価値は物だけでなく、自分自身にも作り出せるんだ。
どんな「性格」も強みにできる
このオムライスに、付加価値をつけてください(P.140)
人にはそれぞれ強み・弱みがありますよね。
言い方を変えれば「長所・短所」「プラス面・マイナス面」など…。
長所も短所も見る人が変わると、逆転する可能性があります。



最近、自分の性格について考えていたんだけど、
「几帳面」って、自分では強みだと思うんだ。



でも、他の人には「細かすぎる」って弱みにも見えるんだよね。



その通り。同じ性格の特徴でも、見る人や状況によって「強み」として評価されることもあれば、「弱み」として捉えられることもあるんだ。



面接などで自己PRをするときは、自分の性格がどのような場面で強みになるのか、具体的なエピソードとともに伝えることが大切なんだね。



そう。自分の短所も、どう言い換えるかで長所としてアピールできるし、自己分析で客観的に自分を見つめることが重要だよ。
第4章 付加価値をつくる考え方
第4章では、付加価値をつくる時の考え方がいくつも紹介されています。
その中のひとつが「わかりやすい化」
分かりやすくすることも付加価値になるんです。
著者が良く使っているわかりやすくするための方法が9つ紹介されています。
この章の中でマイナスの付加価値について著者が述べている部分で以下のように述べています。
ネガティブ、マイナスなことは自分の生命を脅かすリスクにもつながるので、感知能力が高いのです。
このオムライスに、付加価値をつけてください(P.211)



感知能力が高いってどういうこと?



脳が進化の過程で生存に直結する危険信号、つまりネガティブな情報に特に敏感に反応するようになっているんだ。



SNSをやってると、
ネガティブなコメントが気になるのはそういうことなんだね。



ネガティブな出来事がポジティブな出来事に比べて、
2~3倍も強い心理的影響を与えるんだ。



だからこそ、プラスの付加価値よりマイナスの付加価値には注意しなくてはいけないって著者の柿内さんは本書の中で言っているよ。
第5章 付加価値をつくる技術



ついに付加価値をつくる方法がわかるんだね?!



数多くの技術が100ページ以上にわたって紹介されていて、
どれも具体例があって分かりやすい!
ついにこの章では、具体的な付加価値のつくり方が紹介!
本書216ページには、本書内で紹介した技術が一覧となっています。
それぞれの方法が詳細に説明されていて、わかりやすい内容になっています。
具体的な内容はぜひ本書で読んでほしいですが、一部だけ紹介します。
「ずらす法」「分解法」「不なくし」「主従逆転法」
このオムライスに、付加価値をつけてください(P.216~341)
さいごに
本書『このオムライスに、付加価値をつけてください』の内容とは関連ありませんが、
読了後に気になったことをリサーチしてみました。



この本ではオムライスが表紙に載っているけど、
なにか食べるときに何を気にして選ぶ?



やっぱり値段かな、物価高だから少しでも節約したいからね。
みんな同じでしょ?



実際にどうなのか調べてみたよ。
食べ物の3大ワードは「価格・健康・簡単」
「経済性志向」「健康志向」「簡便化志向」が3大志向となりました。
日本政策金融公庫 消費者動向調査(令和7年1月調査)
これは、食べ物を購入する際にどのような点を気にして購入しているかを調査した結果です。
第1位「経済性志向」
物価高の影響で少しでも食費を節約したいという人が多い結果となっています。
第2位「健康志向」
健康というキーワードは売上に大きな影響を与えることが分かるデータです。
第3位「簡便化志向」
簡便化志向とは、料理の準備や片付けの手間や時間を省きたいという考え。



やっぱりみんな節約したいって思ってるんだね!
上位は、だれしもが気にしてるワードになっているね。



だからこそ、いろいろな商品で
「時短!」
「〇〇mg配合!」
などのワードで多くの企業がアピールしているんだ。
この結果を見ると、食の付加価値に関しては「価格・健康・お手軽/簡単」というワードが強いことが分かります。
個人的に気になったのは「国産志向」(原材料はできるだけ国産にこだわりたい)を気にしている人は、
令和7年の調査では11.5%。2年前の令和5年は16.5%だったので、5%ほど低下。
今の食品業界で「国産」というワードは、他の志向と比べると弱くなってきているんだと感じました。
付加価値による許容できる値上げ範囲は「5~20%」まで!



最近は毎月のようにいろいろなものが値上げされてるよね…



2025年3月の飲食料品の値上げは、
なんと2343品目!
2025年3月の飲食料品値上げは、合計2343品目となった。
帝国データバンク/「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年3月



値上がりラッシュで今まで買っていたものも
かなり高くなって、購入を迷ってしまう…



多くの人は「20%」までなら値上げを許容できるみたい!
社会課題に配慮した食に置き換える場合、どの程度の値上げまでなら支払えるかについても、社会課題別に意向を調査しました。いずれの社会課題においても、値上げを許容できる範囲を「5%程度」「10%程度」「20%程度」とする回答の合計が半数を超える結果となりました。
日本総研HPより引用(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=110174)



なんでも値上げしているから
なにか買う時は迷うことが多い気がする…



原材料費高騰など理由はいろいろあるけど、
ちゃんと「付加価値」がついているものを選んで買いたいね。



値段だけじゃなくて、その商品の価値も見極めるってことだね?



これからは「高いからやめる」じゃなくて、
「価値があるから選ぶ」って考え方も大切かもね。
今回は、柿内尚文さんのビジネス書「このオムライスに、付加価値をつけてください」を紹介してきました。
気になった方は、ぜひ手に取ってみてください!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。