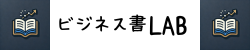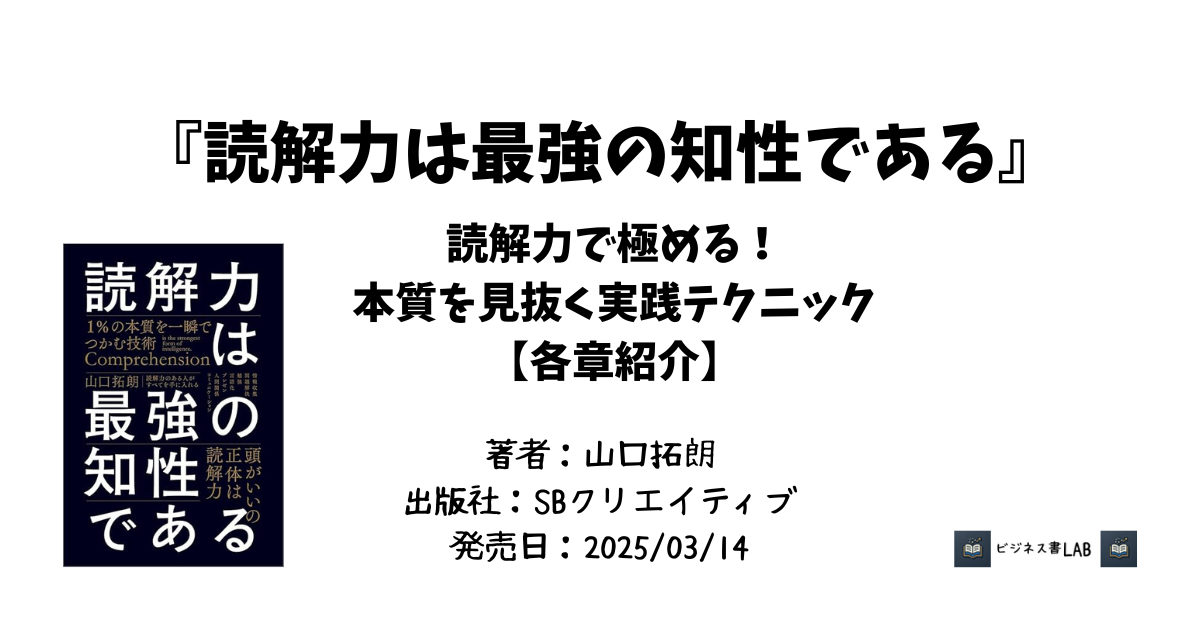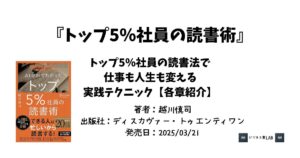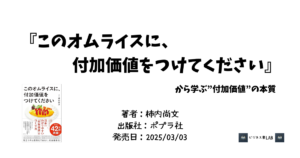この記事では、山口拓朗さんの著書「読解力は最強の知性である 1%の本質を一瞬でつかむ技術」について紹介します。
「読解力は最強の知性である」の概要
本書「読解力は最強の知性である」は、山口拓朗さんの著書です。
| タイトル | 読解力は最強の知性である 1%の本質を一瞬でつかむ技術 |
| 著者 | 山口拓朗 |
| 出版社 | SBクリエイティブ |
| 発売日 | 2025年3月14日 |
こんな人にオススメ
・プロジェクトリーダーやチームリーダーのビジネスマン
・学生や社会人で学ぶことに熱心な人
・論理的思考を磨きたい人
情報過多な現代において、膨大な情報の中から必要な「本質」を瞬時に見抜くスキルは、
意思決定のスピードと精度を向上させます。また読解力を高めることは、情報の背景や意図を深く理解することで自らの成長に繋げることができます。
「読解力は最強の知性である」各章の要約
各章には、どんなことが書かれているのかを部分的に紹介します!
第4章のところでは、本書の内容を少し深堀してみました。
第1章 なぜ読解力は最強の知性なのか

なんで読解力を鍛える必要があるの?



誰でも鍛えられる上に、メリットがいっぱいだからだよ!
本書の中で著者は以下のように言っています。
読解力を高めることで得られる仕事や人間関係でのリターンは計り知れません。
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.40)引用
読解力はどうしてもスキルではなく、生まれ持った才能だと感じる方もいると思います。
しかし、実際には誰にでも鍛えられるスキルなのです。
そして、鍛えることによって得られるメリットが大きいんです!
ネットで一つの言葉を検索すれば、関連する莫大な情報が表示されます。
その中から必要な情報を見抜くスキルは現代人には必須ではないでしょうか。
読解力の三要素は、
1.本質読解
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.50)引用
2.表層読解
3.深層読解
第1章では、この3要素を磨く上で押さえておくべき点を教えてくれ、
さらに読解力を高める5つの基本姿勢まで解説してくれています。
第2章 読解力の前提となる語彙力を鍛える



そもそも、語彙力ってなに?



語彙力とは、知っている言葉の数と、それを使いこなす力のことだよ!
「お腹がすいた」しか言えない人より、「空腹だ」「腹ペコだ」「何か食べたい」といろいろな言い方ができる人のほうが語彙力が高いということになります。
この章では、読解の基礎である「語彙力」の鍛え方を教えてくれます。
語彙力には、2つあると著者は述べています。
語彙力には2種類あります。
ひとつは「理解語彙」で、もうひとつは「使用語彙」です。
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.85)引用



理解語彙?使用語彙?



理解語彙は読んだり聞いたりしたときに意味の理解できる語彙のこと。
使用語彙は実際に話したり書いたりするときに使える語彙のこと。
多くの人は「理解語彙」の方が圧倒的に多く、「使用語彙」はその一部にとどまります。
つまり、しっているけれど使わない(あるいは使えない)言葉がたくさんあります!
この章では、この語彙力を鍛える方法が書かれています。
著者は以下のように言っています。
読書に勝るアプローチはありません。
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.87)引用
著者が本のジャンルごとにどのような読解スキルが鍛えられるか解説しています。



読書は苦手だなぁ…



そのような人に向けて著者がアドバイスをしてくれるよ!
読書が苦手な人はどのようにアプローチすればよいかまでフォローしてくれます!
ここで書かれている読書が苦手な人へのアドバイスは書店で本を購入する人向けです。
Amazonや楽天で書籍を購入する人には難しいように思います。
第3章 本質をつかむための論理力を磨く【本質読解】



この第3章から具体的な方法について解説が始まるよ!
まずは「本質読解」から!
本質とは、物事の根本的な性質や、それがそれであるために必要不可欠な要素のこと。
事象:表面的に見える現象や行動
構造:事象の背後にある仕組みや要因
本質:構造を形作る根本的な原理や価値



事象?構造?本質?余計に分かりにくくなってる気が…



じゃあ「木」を見て考えてみよう!



木?葉っぱや実があるよね?



そうそう、それが「事象」だよ!つまり目に見える部分。
春には青々として、秋には赤くなる。果実なら実がなることもあるよね。



じゃあ、それが本質ってこと?



いい質問だけど、違うんだ!葉っぱや実は変わるよね?
でも、木の形を作っているのは「幹や枝」だよね?



それが「構造」ってこと?



正解!幹や枝がどんな形かで、木の見た目や成長の仕方が決まる。
でもね、もっと大事なものがあるよ。



え?なんだろう?



それが「根っこ」!気が元気に育つには、根っこが大事なんだ。
根っこが弱いと幹も細くなって、葉っぱも枯れちゃう。
だから、根っこが木の「本質」になるんだ。



なるほど!つまり、目に見える葉っぱや実(事象)だけじゃなくて、
その下にある幹や枝(構造)、さらに土の中の根っこ(本質)を
見なきゃいけないんだね!



そのとおり!だから何かを考える時は、見た目だけで判断しないで、
その奥にある「本質」を見つけることが大切なんだ。
著者は、本質をつかむためには以下のように述べています。
文章読解力を高めるためには、「受け身の姿勢」から脱却する必要があります。
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.133)引用
どのように読解力を高めるかを6つのアプローチ方法を教えてくれます。
その際に物事を正しく理解するための重要なポイントも解説。
第4章 「細かい関係性」を理解する【表層読解】
著者は第4章の冒頭でこのように述べています。
大問題!「ちゃんと聞かない人・読まない人」が急増中
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.189)引用
【調査】実際に聞かない人・読まない人は増えている?



読まない人は、そんなに増えているの?



1カ月に本や電子書籍を読まない人は、62.6%もいるんだ
1か月に読む本の冊数は?という問いに対して、
■読まない(62.6%)
文化庁/令和5年度「国語に関する世論調査」の結果の概要より引用
■1,2冊(27.6%)
■3,4冊(6.0%)
■5,6冊(1.5%)
■7冊以上(1.8%)
1か月で1冊以上読む人は、36.9%
調査方法が変化しているため正確に比較はできませんが、
平成30年度の調査では1か月で1冊以上読む人は「52.6%」でした。



なんでそんなに読書する人が減ってるんだろう?



スマホやタブレットなどの情報機器が原因と答えた人が43.6%だったよ
これは過去のデータと比べると、3倍に増えています。



子供の49%が平日に本を読まないってデータがもあったよ。
このデータはベネッセ総合研究所のデータからですが、
以下のような興味深い内容もありました。
蔵書数が多い家庭の子どもや本を読む大切さを伝えている保護者の子どもほど、読書時間が長いことが明らかになりました。(中略)早い段階で読書習慣を身につけた子どもは、その後も長い読書時間を保つ傾向があることもわかりました。
株式会社ベネッセコーポレーション プレスリリースより引用(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001192.000000120.html)
実際に読まない人は増加傾向にありますが、
幼少期の読書環境によってその後に影響していることもデータから分かりました。
この問題から、なぜ表層読解が重要なのかという話に繋がっていきます。
表層読解をするためには、物事の構造を理解する必要があります。
それらを理解するための考え方から説明してくれています。
次に文章読解のテクニックや注意点を具体的に説明しています。



具体例も載っていて分かりやすい!
でも実際に読解力を高められているのかな…



本書のP.276~278をぜひ読んでみて。
そこに載っている文章を読むと、自分の現在地が少しわかるよ。
第5章 クリティカルに聴く・読む【深層読解】



深層読解って言葉からして難しそう…



たしかに見えない部分だからはっきりとした答えはない部分だね
言葉では表現されていない背景や感情のこと
著者はこのように書いています。
大事なのは、その情報について「この理解で本当に正しいのか?」と常に建設的な問いを持つことです。
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.286)引用
今はネットに情報が溢れています、そしてその情報はすべてが正しいわけではありません。
だからこそ、情報を見たり聞いたりしたときに「これって本当に正しいのかな?」と考えることが重要です。
ただ何でも疑うのではなく、「なぜそう言えるのか?」「他の見方はないか?」と前向きに考えることも必要です!
著者は以下のようにも書いています。
同じ事実が異なる真実を生み出すことがある。
読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術(P.289)引用



同じ事実が異なる真実を生み出す?



じゃあここに、水が半分入ったコップがあるとするよ。
これを見て、どう思う?



水が半分も残ってるって思うけど。



そういう見方もできるよね。
逆に「もう半分しかない」って思う人もいるはず。
このように、
事実(コップの水の量)は同じでも、
そこから生まれる真実(受け取り方)は人によって違うんだ。
物事の受け取り方は人によって違うからこそ、いろいろな視点を持つことが大切と著者は言っていると思います。
このようなさまざまな視点を持つスキルを養うためのアプローチを本書は3つ紹介しています。
そのほかに、しぐさ・姿勢・視線や声のトーンなどについても詳しく解説しています。
さいごに
今回は山口拓朗さんの「読解力は最強の知性である1%の本質を一瞬でつかむ技術」を紹介してきました。
本書を読む前は、読解力というワードは身近ではありませんでした。
普段の生活の中で役立つというより、学習時・仕事中などで役立つものだと勝手に思っていました。
しかし、読み終わってみると「読解力」という言葉は多くの人にとって
身近であり、本書を読むことで考え方や見方が変わります!
本書の内容すべてをすぐに理解できるわけではないかもしれませんが、
生きていく上で役立つスキルを手に入れることができる一冊だと思います。
ぜひ気になった方は、手に取ってみてください。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!